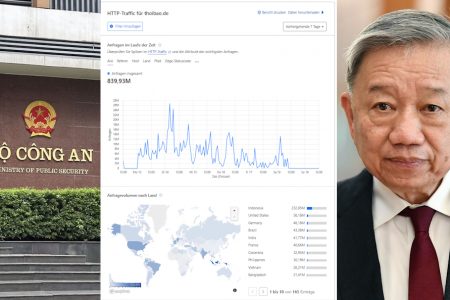今年の丙午正月がどこか沈んでいるのは、必ずしも懐が寂しいからではない。外へ出ると、まるで「規制という地雷原」に足を踏み入れたような感覚になるからだ。くたびれ切って一年を生き抜き、息つく間もなく、罰金を恐れ、検査を恐れる。ほんの些細な一点を誤っただけで、正月のために残しておいた元手が一瞬で吹き飛びかねない。
正月が近づくにつれ、花や盆栽が押収される映像が一気に広まった。個々の案件が正しいのか誤りなのかは検証を待つとしても、それ以上に速く広がったのは背筋の凍るような冷たさだ――痛ましさと怒りである。花は禁制品ではない。それは育てる人の汗であり、年末に少しでも取り戻して「肩身の狭くない正月」にしたいという望みだ。ところが、梅やキンカンの鉢が証拠物件のように運び去られていく。手続きとしては「正しい」のかもしれないが、その正しさは冷淡だ。紙の上では正しくても、人に対しては間違っている。
景気は弱り、購買力も落ち、市場は閑散としている。本来なら必要なのは支援であり、締め付けを緩めることであり、少なくとも情理を備えた対応のはずだ。ところが返ってくるのは、立て続けの「取り締まりキャンペーン」だ。交通、金・外貨、食品安全、原産地追跡、居住登録――そのすべてが、最も弱い立場の人々に集中して降りかかる。結果、小商いの人々は怖くて売れない。零細商人は「確実のため」に店を閉める。正月の街が静かなのは需要が尽きたからではない。まっとうに商っていれば安心して暮らせる、という信頼が尽きたからだ。
最も痛いのは沈黙である。きちんとした説明もなく、いたわりの言葉もなく、機械的な執行が生計を締め上げていることを認めもしない。押収された花鉢は、政策と暮らしの距離の象徴になってしまった。花火がどれほど鮮やかに夜空を染めても、春は完全にはならない――人々に欠けているのはお金だけではない。尊重されているという感覚、そして穏やかに生きられる感覚が欠けているのだ。